「禁酒したことはあるけど続かなかった・・」
「禁酒を続けられるイメージがまったく湧かない・・」
「どうせ禁酒を続けるなんて無理なんだよ・・」
何でもそうだと思いますが、最初からうまくいく人なんてなかなかいませんよね。
それは禁酒についても同じこと。
私は2019年10月以降アルコールを一滴も口にしていませんが、それ以前は上記のような悩みを抱えていました。
そんな私がこれまでの経験や知識をもとに導き出した、禁酒が続かないたった1つの理由。
最初に結論から言いますとそれは・・・
を探すクセがついているから。
※あくまで私の個人的な見解です
「なーんだそんなことか」と思われたかもしれませんね。
でもやっぱりこの1点に集約されると思うんです。
私はこのことを知り、さらには自覚できるようになったことで、禁酒を続けられるようになりました。
今回はこの「飲むための理由」を深掘りし「禁酒から減酒への変更」にも触れていきます。
そして最後には「飲むための理由を探すクセ」を治すにはどうすれば良いかということについて解説します。
この記事を最後まで読むと、なぜ禁酒が続かないのか理解できるようになります。
禁酒が失敗した瞬間を思い出してみると・・

自分自身と交わしたはずの「約束」を破ってしまう瞬間。
その時いったい何が起こったのか?
このことを自分でしっかり分析するのはとても大事です。
ちなみに以前私がスリップ(=再飲酒)してしまったときの「理由」をいくつか挙げてみます。
・嫌なことがあって自暴自棄になり…
・1本だけなら大丈夫だと思って…
これはあくまで私の場合であり、スリップしてしまう背景は人それぞれだと思います。
ただこうやって挙げてみて思ったのは「いやこれ、よく考えると理由になってないぞ?」ってことです。
それはどういうことなのか?
以下で検証してみたいと思います。
実はお酒を飲む理由など1つも無い

さて、先ほど挙げたスリップの理由を分析してみます。
果たしてそれは本当に「飲む理由」なのか?
あらためて1つずつ考察してみました。
そこで見えてきたのは自分自身の「飲むための理由を探すクセ」であり、「実はお酒を飲む理由なんて1つも無い」という衝撃の事実です。
「仕事をがんばったからご褒美に…」
冷静になって考えてみましょう。
仕事をがんばったご褒美がイコールお酒を飲む理由なのでしょうか?
人は自分自身の行為を後から正当化しようとする生き物です。
そもそも「酒を飲みたい」という前提が存在し、「仕事をがんばったから」という理由によってその行為を正当化させようとする。
つまり酒を飲むという目的を達成するために「がんばったご褒美に」という理由を後付けで選んでいるわけです。
しかも無意識のうちに・・・
「嫌なことがあって自暴自棄になり…」
生きていれば誰しも、嫌なことくらいあるでしょう。
むしろ嫌なことがない人なんているんでしょうかね。
いま冷静に考えてみると、嫌なことがあった時にできることは酒を飲む以外にもたくさんあるはず。
ところがスリップしてしまう瞬間というのは、その選択肢がいつの間にか無くなっています。
つまり「酒を飲む以外に選択肢がない」と勝手に思い込んでしまっているわけです。
>>【断酒×アドラー心理学】書籍「嫌われる勇気」を断酒にどう活かすか
「1本だけなら大丈夫だと思って…」
心理学用語の1つに正常性バイアスという言葉があります。
自分にとって何らかの被害が予想される状況下にあっても、それを正常な日常生活の延長上の出来事として捉えてしまい、都合の悪い情報を無視したり、「自分は大丈夫」「今回は大丈夫」「まだ大丈夫」などと過小評価するなどして、逃げ遅れの原因となる。
Wikipedia「正常性バイアス」より引用
そもそも大丈夫じゃないから禁酒しようと決意したはずなのに、時として無駄なポジティブ思考が顔を出すことがあります。
人間の脳というのは厄介で、快感を得るためならどんな屁理屈でも作り出してしまいます。
これも繰り返しになりますが、酒を飲むという目的を果たすために「1本だけなら大丈夫」という、一見まともそうな理由を後付けで作り出しているに過ぎないんです。
「禁酒は無理だから減酒に変更しよう」という理由で再飲酒

他に飲むための理由作りとしては「禁酒は無理だから減酒に変更しよう」というものもありますね。
これも先ほどと同様、酒を飲みたいという前提があり、その行為を正当化させるために「減酒」という理由を後から付けているわけです。
禁酒が必要になるほどの飲み方をしていたのに「量を減らせば別に飲んでもいいよね?」という理由で減酒に変更するのは、私個人としてはお勧めできません。
何故かというと「減酒への変更」はブレーキが効かない状態で徐行するのと同じだからです。
「減酒への変更」はブレーキが効かない車で徐行するのと同じ
自分で自分の飲酒をコントロールできなくなることを車のブレーキに例えることがよくあります。
ブレーキが壊れた車で公道を走るのは非常に危険ですよね?
車のブレーキなら修理すれば直りますが、残念なことに人間の場合は壊れたブレーキは元には戻りません。
一度こうなってしまうと、車に乗らない(=断酒)というのが唯一の選択肢となります。
では「減酒への変更」が意味するものは何か?
それは、スピードを出さなければ、徐行さえしていれば、ちゃんと左右を確認すれば、、、
「ブレーキの壊れた車に乗っても良いでしょ!」
こう言っているのと同じことです。
同じ「減酒」でも意味がまったく違う2つのパターン
私は「減酒」には2つのパターンがあると思っています。
❷飲酒のコントロールができない人が減酒をする
❶は「安全運転」ですが、❷は「ブレーキの壊れた車による徐行」です。
あなた自身のブレーキは今どういう状態ですか?
「飲むための理由を探すクセ」はどうすれば治るか?

ここまでの話をまとめると、そもそも「酒を飲みたい」という前提があり、その行為を「正当化」させるために「理由を後付け」しているということでした。
ではこの「飲むための理由を探すクセ」はどうすれば治るのか?
私が実践していることとして次の2点を挙げてみたいと思います。
❷飲む以外に選択肢はないのかを考えるトレーニング
筋トレじゃないですが、これを日常の中で繰り返して行くことで「断酒力」が鍛えられていくと私は考えています。
❶飲む理由を疑うトレーニング
これは他者の飲む理由を観察し、それを疑ってみるというものです。
例えばあなたの同僚が「よし!今日は花金だから飲むぞー!」と言ったとします。
そこでこう考えるわけです。
(・・金曜日って飲む理由なのか?)
あくまでこれは一例ですが「お題」なら日常のあちこちに転がっています。
アルコールによる社会洗脳が進んだ日本では、トレーニングのネタに事欠くことはありませんね。
❷飲む以外に選択肢はないのかを考えるトレーニング
次に、飲む以外の選択肢について。
先ほどのお題で考えてみると、「花金だから飲む」というのは「酒を飲みたい」というのが前提としてあり、その行為を正当化させるために「金曜日だから」という理由を後付けしているわけです。
では、飲む以外に選択肢はないのでしょうか?
本来は、金曜日だからといって酒を飲まなきゃいけない理由なんて無いはず。
もしも金曜日に酒を飲む以外の選択肢が出てこないのであれば、それは思い込みをしている証拠です。
まとめ:飲酒に理由はない、あるのは言い訳だけ。

この「飲酒に理由は無い、あるのは言い訳だけ」というのは、書籍「禁酒セラピー」の85ページに書かれているフレーズです。
>>「禁酒セラピー」の内容と私の禁酒体験に共通する6つのエッセンス
確かにそうだなぁと今なら分かります。
この記事で何度もお話ししてきましたが、飲酒に理由は無く、言い訳を後付けしているだけ。
本来、酒を飲む以外の選択肢は無限にあるはずです。
これからも「飲むための理由を探すクセ」を治すトレーニングを続けていこうと思います。
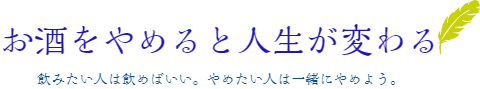



コメント